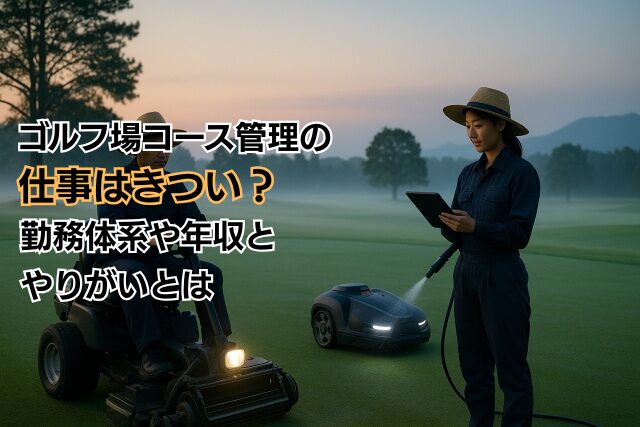ゴルフ場のコース管理の仕事について調べると、「きつい…」という言葉が必ずと言っていいほど出てきますよね。私もゴルフが好きなので、あの息をのむほど美しいコースが、一体どうやって毎日維持されているのか、ずっと気になっていました。
この記事にたどり着いた方は、きっと早朝からの厳しい勤務体系や、特に夏の酷暑、冬の厳寒といった過酷な労働環境について、具体的な情報を探しているんじゃないかなと思います。
実際に私なりに深く調べてみると、重機の操作のようなダイナミックな仕事から、地道な手作業まで業務は想像以上に幅広く、業界全体が抱える人手不足や高齢化といった構造的な課題もあることが見えてきました。体力的なきつさだけではない、多面的なんですね。
一方で、そうしたきつさの対価として、気になる年収や給与の実態、そして単なる作業員で終わらない専門職としてのキャリアパスや資格、さらにはこの仕事でしか味わえない特別なやりがいがあることも分かってきました。
この記事では、コース管理の仕事がきついと言われる具体的な理由を徹底的に掘り下げつつ、向いてる人の特徴、そしてロボット化などの将来性まで、私が調べた情報を分かりやすく、余すところなくまとめてみます。
 ヤマト
ヤマトぜひ、あなたの疑問や不安を解消する参考にしてください。
【記事のポイント】
1.きついと言われる具体的な理由(早朝・季節)
2.仕事内容と必要なスキル(重機・手作業)
3.キャリアや年収、将来性(資格・ロボット化)
4.仕事のやりがいと、向いてる人の特徴
ゴルフ場コース管理の仕事はきつい…の真相
まず、なぜコース管理の仕事がきついと言われるのか、その具体的な理由を深く掘り下げて見ていきましょう。やはり、最大の要因は「早朝勤務」「自然(季節)との戦い」にあるようです。
- 早朝勤務と夏の過酷な労働
- 冬の厳寒とグリーンシート作業
- 重機操作と地道な手作業
- 芝を枯らす精神的プレッシャー
- 深刻な人手不足と高齢化の現実
早朝勤務と夏の過酷な労働


コース管理のきつさを象徴するのが、なんといっても「早朝勤務」ですね。これはもう、この仕事の宿命と言ってもいいかもしれません。
ゴルフ場は、お客様がプレーを開始する(だいたい8時半頃)までに、あの広大なコースという商品を完璧な状態に仕上げないといけません。そのため、出勤は日の出前の朝4時半〜5時頃というのが、一般的のようです。
このきつさは、単に朝が早いことにあるのではなく、お客様のプレイ開始という厳格なタイムリミットまでに、天候や機械トラブルといった不確定要素があっても、必ず間に合わせるという日々のプレッシャーにあるんだと思います。
夏の物理的な「きつさ」(酷暑)
早朝勤務は、日中の猛暑を避けるための合理的な措置ではありますが、もちろん屋外作業であることに変わりはありません。酷暑の中での芝刈りや整備は、文字通り熱中症との戦いです。そのため、ドリンク支給や日よけ設備の設置といった熱中症対策は、任意の福利厚生ではなく、業務遂行に必須の安全管理コストとして認識されています。
夏の精神的な「きつさ」(芝の枯死)
夏のきつさの核心は、実は肉体的なものよりも精神的なプレッシャーにあるかもしれません。
それは、「お客様の要求」「芝の生命維持」という、しばしば相反する要求のジレンマです。
お客様(特に上級者)は、速くて硬いグリーンコンディション(=短く刈られた状態)を理想とします。しかし、芝は植物です。猛暑の中で短く刈り込まれることは、植物としての生存限界を超えるストレスとなり、下手をすれば枯死(こし)してしまいます。
キーパーさんの中には、この行為を「芝を虐めている」と表現する人もいるそうで、芝が枯死寸前になって黄色っぽく見える状態になっても、品質を維持しなければならない…。
お客様の要求と、芝の生命維持という、二律背反の要求の板挟みになるのは、想像するだけでも胃が痛くなりそうです。
夏の具体的な作業負荷
水管理も困難を極めます。日中にスプリンクラーを回すわけにはいかないので、散水は朝夕が基本。しかし、それだけでは水が足りなくなりがちな場所(特に傾斜が強く水はけの良い2段グリーンの段差部など)では、猛暑の中でホースを使った「手撒き」で補水するという、過酷な追加労働も発生するそうです。



夏のきつさは、この仕事の試練がピークに達する季節と言えそうです。
冬の厳寒とグリーンシート作業


夏が芝を生かす戦いであるならば、冬は「芝を守る」戦いです。
最重要作業「グリーンシート掛け」
冬のコース管理で最も過酷と言われるのが、「グリーンシート作業」です。これは、12月〜2月中旬頃まで、ほぼ毎日の日課となる作業だそうです。
目的は、夜間の放射冷却を防ぎ、保温効果を得ることで、霜や凍結による芝の冬枯れやダメージを軽減すること。同時にお客様がパッティングする際の霜を除け、プレイ品質を維持する目的もあります。
この作業のきつさは、個人の庭でさえ非常に大変と表現されるシートの掛け外しを、ゴルフ場の広大なグリーン面積で、気温が氷点下にもなる厳寒の早朝・夜間に行うという、その純粋な物理的重労働さにあります。
霜と凍上(とうじょう)への対策
冬は他にも地道な作業が続きます。寒い地域では、霜が降りた芝への立ち入りは厳禁。踏んでしまうと芝が傷み、春まで回復しない可能性があるためです。
また、霜柱によって芝が持ち上げられ、根が切れてしまう「凍上(とうじょう)」の被害が見つかれば、霜が解けるのを待ってから、平らに押し戻す(転圧する)という、地道な補修作業も発生します。
積雪地域のリスク
積雪地域では、根雪(ねゆき)になる前に「雪腐病(ゆきぐされびょう)」という病気を防ぐための予防的な薬剤散布が必須となります。年に数回しか降らない地域でも、除雪作業を行うべきか、芝への影響を考慮した専門的な判断が求められます。
| 季節 | 主な「きつい」作業 | 物理的きつさ | 精神的きつさ(プレッシャー) |
|---|---|---|---|
| 夏 | 猛暑下の芝刈り 手撒きでの補水 | 酷暑、熱中症リスク 早朝からの長時間労働 | 芝を枯死させるリスク プレイヤーの要求(速さ)との板挟み |
| 冬 | グリーンシートの毎日の掛け外し 凍上補修、雪腐病対策 | 厳寒下での重労働 早朝の暗闇作業 | 霜、凍結、病気による芝のダメージ防止 日々の保護作業のプレッシャー |



冬の作業もまた、夏とは違ったきつさがあります。
重機操作と地道な手作業
コース管理の仕事は、非常にダイナミックな作業と、驚くほど地味な作業の両方で成り立っているみたいです。
ダイナミックな作業としては、グリーンやフェアウェイで使う各種の精密な刈込機(乗用モアなど)の操作はもちろん、コースの改修や造成で使われるブルドーザーやショベルカーといった重機の操作まで含まれます。これはもう、土木業に近い高度な専門技術ですよね。
一方で、コースの美観を保つためには、ゴミ拾いや落ち葉の除去、バンカーを一つ一つ手作業で均すといった、地道で単調な手作業も膨大にあります。
この二面性が、それ自体きつさの一因となり得ます。体力に自信がない方や機械操作が不得手な方にとっては、多様な重機や刈込機の操作習得がきついと感じられるでしょう。逆に、ダイナミックな作業をイメージしていた人にとっては、落ち葉拾いのような地味な作業の単調さがきついと感じるかもしれません。



個々の体力や適性に応じた配置が、重要になりそうですね。
芝を枯らす精神的プレッシャー
夏の労働の部分でも触れましたが、この「芝を枯らすかもしれない…」という精神的プレッシャーは、コース管理、特に責任者であるグリーンキーパーのきつさの核心だと思います。
お客様の要望(速く、硬く)に応えようと芝を短く刈り込めば、芝は枯死寸前になる。でも、芝を大事にしすぎてコンディションが遅くなれば、お客様から「今日のグリーンはダメだ」とクレームが来る。
特にプロが参加するようなトーナメント開催中は、その重圧で夜も眠れないほど気を使うそうです。
もし自分の判断ミス一つで、広大なグリーンを枯らしてしまったら、その損害(高額な「一部の芝の張り替え」費用)は莫大なものになります。つまり、数億円の価値を持つ可能性のあるコース(商品)の品質と生命を、自身の判断一つで預かっているという、巨大な経済的責任まで背負っているんですね。



この重圧は、並大抵のものではないと感じます。
深刻な人手不足と高齢化の現実


個人の努力や適性ではどうにもならない、業界全体の構造的な問題もきつさの一因となっています。それが、「深刻な人手不足と労働力」の高齢化です。
やはり、これまで分析してきたようなきつさのイメージが、先行してしまうようです。
- 勤務地が山間部であることが多い
- 土日祝日に仕事が集中する(世間と休みが合わない)
- 休日が少ないという古いイメージ
- 早朝勤務という特殊なタイムスケジュール
この採用難は、現場のきつさをさらに増大させる負のスパイラルを生んでいます。きついから人が来ない。そして、人が足りないから、既存のスタッフ一人ひとりの負担が増大し、現場はさらにきつくなる…。
ある調査によれば、コース管理部門は「担当社員自体の人数が足りない」が6割、「水準を確保できる能力を持った社員が確保できない」「人材育成が十分できない」がそれぞれ4割強となっており、現場が疲弊している実態がうかがえます。
現状、若手の採用が困難なため、ゴルフ場業界は経験豊富な高齢社員(60歳以降)の活用を積極的に推進しています。しかし、この戦略にも限界があります。
最大の課題は、「健康・体力面の不安が大きい」こと。特に肉体労働であるコース管理業務では、60代後半になるとこの不安を抱える割合が約7割にまで跳ね上がるというデータもあります。
現在のコース管理は、経験は豊富だが体力の不安がある高齢社員と、少数の若手・中堅によって、かろうじて維持されている…



この「健康・体力面の不安を抱えた労働力への依存」こそが、業界の隠れた最大のきつさであり、持続可能性における大きなリスクであると言えるかもしれません。
ゴルフ場コース管理の仕事はきつい…仕事の未来
ここまで、きつい側面をたくさん見てきましたが、もちろんそれだけじゃありません。厳しい側面があるからこそ、その対価として得られるもの、そして業界が変わりつつある「未来」について、ここからは具体的に見ていきましょう。
- 気になる年収と給与水準
- グリーンキーパーへのキャリアパス
- 資格取得は有利になるか
- ロボット化が変える将来性
- 早朝だけの特権と仕事のやりがい
- 向いてる人と向いてない人の特徴
- ゴルフ場コース管理の仕事はきつい…総括
気になる年収と給与水準


「きつい仕事に見合う経済的な対価は得られているのか。これは職業選択において最も重要な要素の一つですよね。
あるデータによると、ゴルフ場(正社員)の平均年収は約379万円だそうです。ただし、給与分布は314万円〜717万円と、その幅が非常に広いのが特徴です。
この幅は、何によって生まれているのか。それは、役職とスキルです。求人情報などから実例を見ると、キャリアパスと年収の相関が見えてきます。
| 役職 | 想定される業務内容 | 年収(実例) |
|---|---|---|
| スタッフ(平均) | 芝刈り、バンカー整備、清掃など | 約379万円 |
| サブキーパー | 現場の実務リーダー、中核スタッフ | 400万円台 |
| グリーンキーパー | コース管理責任者、科学的分析、造成、管理計画 | 480万~550万円 |
分析の結果、平均年収(約379万円)と、専門職であるグリーンキーパーの年収(480万~550万円)との間には、100万円以上の顕著な差が存在することが確認できました。
これは、次のセクションで詳しく見るキャリアパスが、単なる名誉職ではなく、明確な経済的インセンティブ(報酬)によって裏打ちされていることを示しています。キャリア初期のきつさを乗り越え、専門性を高めることができれば、平均以上の収入を得られる業界構造があると言えそうです。
また、きついというイメージを払拭するため、労働条件の改善に取り組む企業も見られます。求人例の中には、「完全週休2日制」「年間休日122日」といった、ワークライフバランスを重視した条件を提示するものも存在しています。
ここで挙げた年収は、あくまで求人情報などに基づいた一例です。実際の給与は、勤務するゴルフ場の規模、地域、本人の経験やスキル、役職によって大きく異なります。また、福利厚生(住宅手当、家族手当、早朝手当など)の内容も企業によって様々です。



必ず、個別の求人情報で具体的な条件をしっかり確認してくださいね。
グリーンキーパーへのキャリアパス
多くの人がきつい肉体労働をイメージする一方で、この職業には明確な専門性とキャリアパスが存在します。初期のきつさは、実はこの高度専門職に至るためのエントリープロセスとしての側面が強いんです。
多くのゴルフ場では、未経験者であっても明確なキャリアステップが用意されています。
入社後はOJT(On the Job Training)研修が中心となり、ゴルフ場の様々な仕事を実地で経験します。3ヶ月後や3年目といった節目でフォローアップ研修が組まれ、キャリアの方向性を再確認する機会が設けられていることも多いようです。
現場の実務を担う中核的なリーダーとして、後輩の指導やキーパーの補佐を行います。
未経験からでも、OJT研修を経て、将来的にはコース管理の最高責任者であるグリーンキーパーや、ゴルフ場の所長へのキャリアパスが開かれています。
そして、この最高責任者であるグリーンキーパーの職務は、単なる現場の監督者ではありません。その職務は、肉体労働から、「科学者・技術者・芸術家」としての側面を併せ持つ、高度な専門職へとシフトします。
科学者として(教養)
土壌の水分量や葉の栄養状態を、外部機関とも連携しながら科学的に測定・分析します。その科学的根拠に基づき、肥料や薬剤の最適な管理(いつ、何を、どれだけ投与するか)を実践します。経験と勘だけでなく、データに基づいた管理が求められます。
技術者として(パワー)
芝刈り機のみならず、ブルドーザーやショベルカーといった重機に自ら乗り込み、コースの造成や改修まで行うこともあります。コースの地形を理解し、それを実現する高度な操作技術が要求されます。
芸術家・設計者として(感性)
植栽の管理や、海外の気鋭なコースデザイナーの意見を取り入れながら、モダンなコースデザインやレイアウトの設計・改修にも関与します。コースの戦略性だけでなく、「美しさ」をも追求する感性が必要です。
責任者として(管理)
プロゴルファーが参加するトーナメントの、舞台をセッティングします。プロの技術レベルを考慮し、グリーンのスピードや硬さを大会基準値に完璧に整えるための、長期的な管理計画を策定・実行します。



このキャリアパスの存在は、初期の物理的なきつさが、深い専門知識(教養)、高度な操作技術(パワー)、そして美的センス(感性)を要求される高度専門職になるための「エントリーチケット」であることを示していると、私は感じました。
資格取得は有利になるか


この分野の専門性を客観的に証明する資格として、「芝草管理技術者」という資格が存在します。
この資格は、なんと日本ゴルフ協会(JGA)によって公認されており、ゴルフ界の発展に寄与するものとして高く評価されています。
専門資格と聞くと難しそうですが、エントリーレベルの3級は、18歳以上で所定の研修(eラーニングなど)を受ければ、実務経験がなくても受験が可能です。試験は芝草に関する基本的な知識を問う筆記試験(90分、50問)で、60点以上が合格の目安とされています。



キャリアアップを目指す上で、自身の専門性を客観的に証明し、意欲を示すために非常に有効な資格と言えそうですね。
ロボット化が変える将来性
セクションVIで触れた、業界の深刻な課題(人手不足、高齢化)。これらを解決する鍵として、テクノロジーの導入、特に機械化と自動化が急速に進んでいます。
その具体的なソリューションとして、ロボット芝刈り機(例えば「HerbF®」のような技術)が登場しています。
- 機能: 既存の使用している芝刈り機に外付け機器を搭載するだけで、自律化(無人化)することが可能です。
- 方法: 特に注目されているのが「ティーチング・プレイバック方式」。これは、ベテランキーパーによる芝刈り機の操作を学習し、その作業データを自動で記録・再生する方式です。
- 安全性: もちろん、前方の障害物(人や物)を感知し、自動でブレーキが作動する安全機能も搭載されています。
この技術の核心は、単なる無人化による人手不足対策に留まらない点に、あると私は思います。
「ベテランキーパーの作業データを自動記録」する点。これは、業界最大の課題であった労働力の高齢化と技能継承の問題に対し、ベテランの暗黙知(言葉にできない熟練の技)をデジタルデータとして次世代に継承するという、画期的なソリューションを提供するものです。
テクノロジーの導入は、コース管理のきつさの質を、物理的な反復労働から「技術的なシステム管理」へと確実にシフトさせていく可能性を秘めています。



将来のコース管理者は、自ら芝を刈るのではなく、ロボットのフリート(集団)を管理し、土壌データを分析する「テクニカル・マネージャー」としての役割を強めていくと予想されます。
早朝だけの特権と仕事のやりがい


分析してきた、数々のきつい側面。それらを上回る、この仕事特有の「やりがい」も多数報告されています。これこそが、多くの人がこの仕事を続ける理由なんだと思います。
- 達成感と美意識: 「自分が整備したコースを多くのゴルファーが利用しているのが嬉しい」 「芝が美しく揃った朝の景色は、毎日見ても飽きない」
- 誇り(プライド): 「担当ホールがプロの試合に使われたときは、本当に誇りを感じた」 「トーナメントという晴れの舞台を、裏側から完璧に支える責任感」
- 自然との一体感: 「自然と共に働くという、オフィスワークでは絶対に得難い魅力的な側面がある」
- 顧客からの評価: 「プロや常連客から『今日のグリーン最高だね、ありがとう』と直接感謝の言葉をもらうことが、日々のモチベーション維持に大きく貢献する」
ここで特に注目すべきは、きつさとやりがいの表裏一体性です。
この仕事の最大のきつさの一つである、早朝4:30出勤。これを耐え抜いた者だけが、最大のやりがいの一つである「芝が美しく揃った、誰の足跡もない朝の景色」を独占できる。



これは、プレイヤーや一般人には決して見ることのできない、管理者だけに与えられた特権的な報酬であると、私は感じました。
向いてる人と向いてない人の特徴
さて、ここまで分析してきた内容を総括して、ゴルフ場コース管理の仕事にどんな人が向いていて、どんな人が向いていない可能性が高いか、私なりに整理してみます。
向いていない可能性が高い人
- ライフスタイル的に、早朝(4時台)の起床を継続することがどうしても不可能な人。
- 天候(酷暑、厳寒、雨天、多湿)によって体調や精神状態が大きく左右されやすい人。
- 落ち葉拾いやゴミ拾いといった、単調な手作業の継続に強い苦痛を感じる人。
- あるいは逆に、ブルドーザーや精密機械など、重機や機械の操作習得に強い抵抗がある人。
- 友人や家族と休みを合わせたい(土日祝日の勤務に強い抵抗がある)人。(業界の特性上、土日祝が繁忙期のため)
向いている可能性が高い人
- 早朝の「きつさ」を、静謐な朝の空気や美しい景色という「やりがい」に転換できる人。
- 自然の中で、芝という「生き物」を相手に、科学的なアプローチ(データ分析など)で物事を管理することに喜びを感じる人。
- 目の前の物理的な「きつさ」の先に、「グリーンキーパー」という高度専門職へのキャリアアップを目指す、長期的な視点を持てる人。
- ロボット化やデータ分析など、新しい技術を学び、それを現場に適応させていくことに興味がある、あるいはワクワクする人。



ゴルフ場の管理に興味があるのであれば、自身の性格や考え方などを客観的に捉え検討してみてください。
ゴルフ場コース管理の仕事はきついのか…総括
最後にあなたへ、今回の結論をお伝えします。
調べてみた結果、きついのは紛れもない事実だと分かりました。それは「早朝勤務」「過酷な季節変動」「慢性的な人手不足」、そして「高度な専門的責任」という、多層的な要因に起因するものです。
しかし、そのきつさは、キャリアパスと明確に連動していました。キャリア初期の物理的なきつさ(早朝・天候・肉体労働)は、経験を積むにつれて、芝の生死を預かる精神的なきつさ(=責任)へと質的に変化し、それに見合う給与と専門的地位(グリーンキーパー)が付与される構造となっています。
そして何より、業界は今、人手不足と高齢化という深刻な課題と、ロボット化に代表される技術革新の岐路に立っており、仕事のあり方そのものが変わろうとしている変革期の真っ只中にあります。
ゴルフ場コース管理は、ただきついだけで終わる仕事ではありません。



その先には、深い専門性と、自然を相手にする仕事ならではの大きなやりがい、そして新しい技術と共に未来を創っていく可能性が広がっています。
【参考】
>>ゴルフ場のフロントは美人が多いって噂は本当?理由と仕事の裏側とは
>>ゴルフ当日キャンセルはOK?体調不良時の連絡マナーや料金の全知識